遠足とは何ぞや?
昨日の学年会議のレジュメに、一昨日行われた
高校最後の遠足の総括を生徒に促すようにとの、
一項目がありました。
議長が集合して、学年協議会で論議をして、それを
再びHRで議論し…を学年主任会議が指導した今回の行事。
うちのクラスの遠足は、主任から「直前に行き先が変わるなんて、
計画性が…」と議長がお叱りを受けましたが、
担任も副担も、参加した生徒はおそらくみんな、きっとそれなりに
楽しめました。それなりに、というのが、生徒同士の気遣いの
結果かと思います。
楽しい思い出を!!というより、居心地の悪い思いをする人が
いないように!
4月に組替えして、テスト直後の年度最初の
生徒主体企画・運営行事。
そんな気遣いを感じた一日でした。
まず、「アウトドアなら、ウチらに任せて料理選手権」の開催
(担任&副担主催)を発表し、班内のメニューや材料調達の議論を
通じて、関係を築かせる仕掛け。

議長&レク係の「奮闘」(主には校内での協議・調整)で、湖畔の
雨天対応のベストプレイス&プライスのBBQグッズレンタル店の
予約も完了。
当日、担任&副担のサプライズで賞状と賞品、全員分の参加賞
を用意していったのですが、サプライズは生徒のほうが数段上。
これがBBQで?というような煮込み料理やトッピング充実の
デザートまで登場、審査に苦労しました。
さらに、「これは審査対象ではありません。審査の一皿まで、
先生がお腹、空いてはらへんかなーという『気遣い』です。」
と料理を差し入れに来る班も。(ワイロ??)
ヨット部の生徒がいて、雲と風向きを読めたため、
にわか雨の合間を縫ってのレクも順調に進行。
ほかにも、みんなに知られていない得意技を披露できた
生徒が何人もでました。
(レクは、自分たちで歌いながらマイムマイムやったんですよー♪)
精算・片づけもスムーズでした。
そして表彰式。
担任・副担・議長のそれぞれが賞を授与、無事帰途につきました。
私たち教員にとって、一番うれしかったのは、
最後にクラス集合写真をとって解散のはずが、解散の指示のあと、
班ごとに写真を撮り始めたこと。
担任・副担とも20年以上の教員生活で初めてのこと。
キュンとなりました。
遠足でキュン、いいもん、見せてもらいました。
しばらく、がんばれそう☆

京都 岸田康子
月: 2012年5月
【告知】大阪高生研 6月例会文化祭見てあるきDVD上映会 & ぴらっと一枚実践交流
大阪高生研6月例会担当・平田です。
以下、どうぞお越しください。
新年度が始まって2ヶ月が経ちました。
新しいクラスや学年、あるいは学校で、不安に思っていること、悩んでいることはありませんか?不安や悩み、実践のことを話し、聴き合えていますか?
「ぴらっと一枚実践交流」(ぴらいち)では、普段の実践をグループのなかで報告し合い、実践交流をします。グループのなかで実践を報告し(10分)、「聞き込み」に答えていきます。そのなかで、意識していた、あるいは無意識だったことが明確になっていきます。そして、グループの仲間が、「ほめ」「けなし」「まとめ」の視点から、必ず評価してくれます。
逆に、仲間の実践報告を聞き込み、ほめ、けなすなかで、共感できたり、失敗から学んだり、少しほっとすることができます。
「ぴらいち」には、皆さんの実践報告が必要です。A4用紙一枚に、実践の一コマを切り取って、書いてきてください。うまくいったこと、失敗しちゃったなぁと思うこと、いま悩んでいること・・・などなど、何でもけっこうです。かっこつけずに、肩肘を張らずに、ありのままの実践を書いてきてください。
気を張らずに実践交流ができる「ぴらいち」を、一緒にしませんか。
日時:2012年6月10日(日) 14:00~17:30(13:30開場)
「文化祭見て歩あるき2011」DVDを30分間上映した後、「ぴらいち」を行います☆
場所:大阪市立市民交流センターなにわ
JR大阪環状線「芦原橋」駅下車、南口改札南へ徒歩2分
または、南海高野線「芦原町」駅下車、東へ徒歩5分
※実践報告を40部、印刷のうえ持ってきてください。お願いします。
お問い合わせ、参加のお申し込みは、
http://kokucheese.com/event/index/39212/ まで。
サッカー岡田監督に学ぶ
NHKプロフェッショナル仕事の流儀5月21日放送【日本代表から、中国へサッカー岡田武史監督初密着!チーム舞台裏W杯、敗戦と挫折】のテレビを見た。
勝つための戦術を教えるのではなく、選手たちが戦術を考えてチームとしてどのように戦うかを決めていくことが重要という課題は、生徒達を指導する場合も、示唆に富んだ重要な指摘だと感じた。勝つための戦術優先ではなく、自発的に選手たちが問題点に気付いていくことが重要で、それをもとにチームのメンバーで戦術を相談し、決定していくプロセスを大切にしている。受け身では成長しないと岡田監督は言っている。
われわれも、様々な環境の中で育った生徒たちを抱えて「十八才を市民に」と取り組んでいるが、課題はさまざまである。彼らが自分で気づき、取り組むことがもっとも重要なのではないかと改めて考えた。
大人との関係が作れない
このごろ、東京の定時制高校の在籍の30~40%が中学時代の不登校経験者である。Aも中学時代不登校経験者で4年生になり、私が課題研究の担当になった。Aは大人との人間関係がうまく作れず、一学期は、かなりAに注意した。Aには言ってやらないと卒業したら社会に適応できないのではないかと言う懸念があった。アルバイト先では、先輩とケンカをして、すぐにやめてしまったということを聞いていた。
Aは、自分の責任になることを極力さけるのである。たとえば、Aが私に「ここはどうやるのですか」と聞くが教えてやっても自分ではなかなかやろうとしない。教師がやってやると失敗したら教師のせいにできる。また、自分がやって失敗したら、教えた私のせいにする。自分の責任を言われるのがいやで、自分でやらないようにしているのである。結局、自分で判断し行動をし、その責任を取ることをしないのである。また、私にため口で話し、必要なものを持ってくるように頼む。「おれはおまえの担当だが、使いパシリではない」と何度か注意した。私の指導に自分の行動を反省し、冷静になったときに謝ってくることもあった。
担任の指導もあり、二学期は注意をすることが少なくなったが、二学期の終わりに、最後に指摘したのは、報告書の内容であった。課題研究で取り組んだ課題を決めるとき、楽なものを決めたくて、友達が自分に勧めたものに決めた。結果的には、作るのに時間がかかり、作業も簡単ではなかった。課題研究の報告書の「はじめに」のところで、この課題を選び、大変だったのは友達Bのせいであると書いてきたのである。私は「君は友達を無くすよ。君が友達に相談し、友達がアドバイスをしたのに、それを自分で選んでおいて、友達が勧めたのが悪いというのでは、だれも君の相談には載らないし、友達になろうとはしなくなる。」と諭した。さすがに二学期の後半であったので私が言いたいことが理解できたのか、反論はせず、納得したようだった。
支え合う彼ら
そのAに、アドバイスをしたのも中学時代不登校経験者のBであった。彼も先生に対して敬語を使えないなど課題をもっているが、担任によると二人はお互いに支え合っているから4年間学校に通えたのではないかと言っていた。お互いにゲーム好きで甘えたところがあるが、Aは話し好きでBに話しかけをし、話し下手なBはそれに応じる形で話をしていた。Aがいなかったら、Bも学校が続かなかったのではと担任が話していた。彼らは「支え合っているのだなあ」と感じた。
卒業式の日にAは、職員室に「4年間ありがとうございました」とお礼に来た生徒の一人になっていたのは嬉しかった。
K(東京)
とりあえず“伝家の宝刀”を捨ててみた
4月の定期異動で学校が変わり、2年ぶりに担任を持つことになった。1学年3クラスの小さな学校で、担任以外の分掌も多く回ってくることは予想されたが、人権教育主任、図書部長、保体環境部(保健部と環境部が一緒になった部)、吹奏楽部顧問、アーチェリー部顧問ときたから驚いた。とにかくどこでどううまく手を抜き、かつ「意味のある」仕事をしていくのかを考えながらの毎日である。
4月当初からクラスで起きたことと言えば、入学式翌日の朝から殴り合いのケンカ、真面目な生徒があまりの授業中のうるささに耐えきれずものすごく大きな音を立てて飛び出し行方不明になったり、クラス内での盗難、入学式当日から休んだ生徒がいて保護者とも連絡も取れない状態が3週間ほど続いたり、中間テストの最中にふざけて咳払いや机を指で鳴らしての妨害行為(4人が保護者を呼び出しての教頭・生徒指導部長による説諭)、授業中に連続して何人もの男子生徒によるジュース飲み(教科担当が私に訴えてきた)などなど、ここには書けない警察沙汰のこともあったりが続いた。それらのことに『ピンチはチャンス』『困らす生徒は困っている生徒』『生活が指導する』『個人ではなく集団の問題として考える』など、高生研で学んだことをフル動員して臨んできた。と書けば格好はいいが「手抜き」の毎日である。
朝は7時に出勤し、夜は7時、8時、遅いときは10時まで学校にいなければ回していけない日もあった。2週間ほど微熱が続き、先日は熱発39℃でうなされた。
「手抜き」の一つを紹介する。これまで担任をしていたときは、日刊で学級通信を出していた(高生研から学んだことのひとつ)。ある先生は通信のことを「伝家の宝刀」と呼び、私もそのクラスに与える効果・影響は大きいものと信じ(今も)、多くの場合楽しみながら書いていた。生徒の成長や変化、生徒同士の関係性に視点を当てて書かれる通信は、生徒同士、保護者、そして私を含めて「学び」のある空間をつくり出す媒体であった。しかし一方で、「文章嫌い」の私にはときに大きな苦痛を伴う作業でもあった・・・。
現在、入学式から1ヶ月以上が過ぎた。出した通信は入学式のときに出した1号のみ。それ以降は出していない。
ただ、その代わりにやっているのが「学級日誌」の活用。きっかけ(ヒント)は2つある。1つは熊本高生研のF川先生の授業ノート。毎時間、交替で生徒に「その日の授業内容・感想・質問など」を書かせて、次の授業の最初でそれを皆の前で読みあげ、それに対して先生がコメントをするという応答のある実践。もう1つは、熊大のS石先生がよく「学級通信を毎日出すなんてものスゴイ労力が必要じゃないですか!担任業務がただでさえ大変なのに本当によくやりますよね!日刊通信の主旨や意義は分かりますが、もっと他の方法はないのですか」というようなことを言われていて、「確かにそうだなぁ」と思っていた。
とにかく通信でやっていたことを「学級日誌」でやっている。なかなか生徒は書かない子(書けない子?)も多いので、応答のある実践にはなっていないもののこれまで通信で書いていたことを気軽にバンバン日誌に書いていっている。それを必要に応じて朝や帰りのSHRで話す。これはやってみて、思ったよりうまくいっているように感じている。熊本の学習会で報告して分析していただけたらなぁ、ともくろんでいる今日この頃です。
(田中克樹)
東京大会の受付、千葉高生研からのお知らせ
5月28日現在の大会参加申込数は24人です。県別は下記のようになっています。
大阪3
北海道2 千葉2 埼玉2 東京2 滋賀2 沖縄2
青森1 秋田1 群馬1 長野1 愛知1 京都1 三重1 鳥取1 熊本1
まだ、参加申込書などが届いてない支部が多いと思いますが、届きましたらなるべく早く申し込んで下さい。なお、ホームページ上にまだリーフレットと申込書がアップされていません。原稿が揃わないようで困ったものです。揃い次第掲載されると思いますので、そちらもご利用下さい。
一般分科会 実践報告 「A男の成長に関わって」 谷崎嘉治氏
青森から、今年の全国大会に谷崎さんが実践報告します。
小学校時代は優等生、中学校時代も1年時は部活動で頑張っていた生徒でしたが、問題行動を重ね、中学校の担任から罰として丸坊主を言い渡されたことをきっかけに不登校、ほとんど中学校では学ぶことなく遊んでいたひとりの生徒。彼は中学校の卒業式にも参加させてもらえませんでした。
私立高校には合格できるだろうと受験したが、不合格。最後に辿りついたのは定時制高校。そこで出会ったふたりの教師。ひとりは谷崎さん。そして、もう一人は、昨年の8月に30代の若さで病気のため亡くなった八甲田山のトトロこと一戸 直道さん。
一戸さんの国語の特別授業で東日本大震災のボランティアとして参加した労働組合員の話を聞いて谷崎さんと一緒に岩手県へ。
生徒会活動を通して彼が学んだことは何か。中学時代にはまったく勉強しなかった彼が、生活体験発表に書いた原稿用紙は10枚以上。数学や物理を勉強したいと言いだしたのはなぜか。
定時制高校の中にもくさったみかんを排除しようとする教師が残念ながらいる中、彼の成長を温かく、時には厳しく見守る指導は、今、私たちが原点に立ち返って考えていかなければならないことではないだろうか。
ひとりひとりの生徒の言葉を大切にすること、
これがひとりひとりを大切にすることの第一歩である。(一戸 直道)
青森高生研 吉田
本の紹介(「カッコいいほとけ」・熊本高生研通信211号から)
おすすめのl冊
早川いくを・著 寺西 晃・絵
『カッコいいほとけ』
(幻冬舎・1200円+税・2011年刊行)
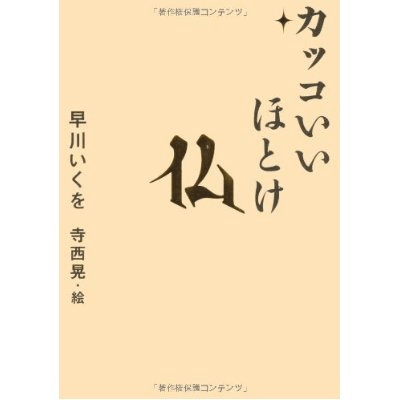
私(福永)は世界史の教員ですが、古代インドのスーパースター”お釈迦様”の教えだけは、どうもうまく説明できません。「六道輪廻」とか「解脱」とか「悟り」とか、辞書的な語義は分かっても生徒が(自分自身も)納得するような言葉がどうしても出てこないのです(福永の生家の宗教(宗派)は浄土真宗ですが、三十過ぎた頃に父に聞いてやっと判明したという罰当たりな檀家に過ぎません)。毎年インドの授業をどうしようかと悩んでいた際、たまたま出向いた書店で目についたのが本書『カッコいいほとけ』でした。
早川いくを氏はベストセラーとなった『へんないきもの』の著者でもあります。早川氏の名前に惹かれて、どんな本かなと立ち読みし始めたら、これが福永のツボにピッタリはまる本でした。何せ帯にある惹句が「イカしたキャラの御仏(みほとけ)たちが大集合!!」なのです。前書き(プロローグ)で気になるフレーズを抜き出してみると「…こういった時代の流れの中で、やがてまったく新しいムーブメントが起こる。大乗仏教である」、「(大乗仏教は)厳格なクラシックの演奏が、フリージャズになったようなものである」、「本書は、そんなほとけたちの魅力を余さずご紹介……するようなことは一切なく、ただひたすら、かっこいいほとけを、かっこいい、かっこいいと礼賛するだけの本である」など、いかがわしさ満載です。本文もギャグ(のみと言っていいほど)を交えた文章で、28柱(?)の仏たちを紹介しています(有名どころでは、帝釈天、阿修羅、阿弥陀如来、不動明王などなど)。しかし、笑って読み終えたら(立ち読みで小1時間)何と「仏教(とその他のインド宗教)の基礎知識」が身についている(?)ではありませんか!活字も大きく短時間で読了できますし、その割には、迫力あるイラストも含めて読み応えもあります。
早川氏が「仏萌え」して勢いで書き下ろした(一見)怪作ですが、若者向けの教養書としても見逃せません。ちなみにMy favoriteは十二神将(ほとけ戦隊)の中で頭に兎さんを付けた卯(う)神将です。仏様に対して失礼ですが、笑えます。(文責・福永 信幸)
全国大会回想記 その②
大阪高生研の西村です。前回は、わたしがはじめて参加した1991年の京滋大会のことを書きました。今回はその続きです。
さて、1992年の全国大会は今年と同じ東京で行われました。前回同様、同僚の先生に連れられて、物見遊山の上京でした。20年前でほとんど記憶にない中で、2人の女性が鮮烈に印象に残っています。といっても、「女性」というジェンダーで括ってしまうと、お2人に叱られてしまうでしょう。当時はまだ「ジェンダー」という言葉が世間では流布していない時代でしたが、この20年で「ジェンダー」という概念が広まった背景に、このお2人は相当貢献をなさったのではないでしょうか。
そのおひとりは、現社民党の代表を務めておられる福島瑞穂さんです。当時は名前こそ売れてはいましたが、もちろんただの人権派弁護士というだけの方でした。政界に出られるとは思ってもみませんでした。せっかく東京で大会をするので、東京在住のネームバリューのある方にお話を聞くという交流会企画だったと思うのですが、いまから思うとたいへん貴重な経験をさせていただきました。
もうおひとりは、吉田和子さんです。たぶん問題別分科会だったと思うのですが、文化祭指導について話をしていただいたと記憶しています。このとき初めて「実践家」という言葉を耳にし、また、HRで取り組む文化祭の出し物を、強引に「劇」にもっていくやり方に、違和感をもったものでした。まもなく高生研でお顔を見ることがなくなるのですが、2002年北九州の布刈会館で行われた九ブロで再会して親しく話をする中で、当時抱いたイメージとは全く異なる方だったことに気付きました。
さて、東京ではもう1度、7年前に全国大会が開かれていますが、これはまだ皆さんの記憶にも新しい大会だと思います。この大会ではじめて応援ブログなるものが導入され、今回と同じように月に1回のペースで原稿を書きました。また、元劇団四季の羽鳥さんを招いてのワークショップが印象に残っています。前泊も含めて3泊だったのが2泊になったのもこの大会からだったでしょうか?講演会を初めて導入したり、大会終了後に大交流会がおこなわれたり、“新しいスタイルの大会”という印象が強い大会でした。
(つづく)
楽しいからやっただけです
「すてきな合唱、すばらしかった!ほんとに、AくんIくんたちの力やわ~。」
「いや~、楽しかったしおもしろかったっす。楽しいからやっただけです。」
「仰げば尊し」を歌うのが慣例であった私たちの学校の卒業式に、交渉の末「前例としない」ことを条件に生徒が選んだ歌を歌わせる方針をとったのが私たちの一つ上の学年でした。私たちの学年はどうしましょう?と昨年度の11月に5人の担任で話し合った末、「生徒の希望を聞きましょう」ということになり、全生徒にアンケート実施。その結果「歌は自分たちで選びたい」との回答が三分の二を占めたため、有志生徒を募って卒業式プロジェクトチームを立ち上げました。その時出てきてくれたのがAくんやIくんたちでした。昼休みにお弁当持ちで集まって話すうちに、「オレらの卒業式は何かを二部合唱したい」ということになり、何度も生徒アンケートを重ねて曲を絞り込み、“いきものがかり”のYELLに決まりました。
練習時間がほとんどない条件の中で200人の卒業生の二部合唱ができるだろうか?…少し合唱を知っている私は疑いましたが、とりあえずAくんIくんFくんHくんYくんの有志5人と私とで男子パートの練習を始めました。5人とも熱心でしたが、大きく音をはずすことなく歌えるのはAくんだけで…。しかし毎日昼休みに一緒に歌うのがとても楽しいらしく、そのうちに仲間を連れてくるようになりました。同心円が次第に大きくなるように練習の有志参加者が増えていったのでした。(女子パートは楽譜を読める人を中心に自主練習が進んでいました。)しかし、なかなか男女で「ハモる」ところまではいきません。学年全員参加の練習を3学期に数回行ったのちに、吹奏楽部のBさんに指揮を頼み、2月29日の卒業式予行でいよいよ最後の練習となり…。
卒業証書授与の時には名簿順に前を向いて座っている生徒たちが、合唱の時だけ保護者席に向き直りながら男女別に並び直します。男子が前・女子が後ろと決められた指定の合唱体形への移動から歌までを練習しました。男声女声の掛け合いがうまくあわない、男声の音が外れる、女声が弱い、等々の問題点が浮かび上がりましたが、私は「仕方ない、妥協しよう。歌うだけで十分。」と考えて、あまり指摘しませんでした。ところがプロジェクトチームからもそれ以外の生徒たちからも、「バラバラで合唱になってません」「男女の立ち位置を逆にしたほうがいいと思います」「女声が弱いから聞こえなくて掛け合いがあいません」という、もっと良くしたいという意見が次々と出てきました。予行練習終了の時間が迫っていたのですが、私は「しゃべっていい?」とプロジェクトチームに許可を得てマイクを握り、「女子が前で男子が後ろに変更します。各クラスの音量が最も大きくなるだろうと思われるように工夫して並んでください。時間が迫っているから15秒でやって。」と言いました。どのクラスも10秒かからずに並び直していました。男女とも、声の大きい人たちを前方に集めていました。その後もう一回行った練習では見違えるように音量が増え、そのまま卒業式当日の合唱へとつながったのでした。
「田中先生が並び方を生徒に任せた時は『なんてことするんや!』と思いましたけど、うまいこといってびっくりしました。」と他の先生が言ってました。ホントに、うまくいってよかったです。
(京都:田中)
「実践分析を科学する」
今年の全国大会で、熊本の白石陽一さんと組んで次のようなテーマで問題別分科会
を行うことになりました。
テーマ:「実践記録・その読み開き方 ~実践分析の方法論を学び合おう~」
高生研の研究活動の醍醐味は何と言っても実践分析です。
これは、その実践分析そのものを学びの対象にしようという新しい試みの第1弾
です。
うまくいけばシリーズ化を考えています。
明日からのサークル例会運営に役立つ方法論を学ぶ、というばかりでなく、
実践分析の方法を学び合うことで、生活指導の理論と実践を学ぶ、ということが
中心テーマです。
ただし、提起者の話を聞くだけではなんてことはないので、
与えられた時間の半分は実際の実践を分析しながら、提起されたことを確認する
というワークショップ的な運営にしたいな、と思っています。
興味のある方、是非参加して下さい。
現在、ワークショップで取り上げる実践、募集してます。推薦・立候補お願いし
ます。
(絹村俊明)
門前の小僧
現在の勤務校に転勤すると共に高生研に加入し、28年間経ち、定年退職しました。工学部出身なので、教師の勉強はほとんどしておらず、教育学部出の先生には引け目を感じていましたが、とらわれずやった自己流でも通じたのは、若さからだと思います。若さが足りなくなると、それ相応の技術も必要となります。
そんな中、何も考えず高生研にはいると同時にたった一人の県の事務局となりました。全国委員会に一升瓶を必ず持って行くことだけを教わり、ふたき旅館に来ました。難しい言葉が飛び交い、夜遅くまでの激論、大変なところだと思いました。それでも、出来るだけ参加したのは、秋田に帰ると何となく「やるぞ」という気分になったからです。何か分からないけど元気が出たのです。何年も参加していると、門前の小僧何とやらで、高生研風の考え方で学校を見るようになったと思います。でもやっぱり、学校や教師を変えるのは難しい。
高生研が新しい道を進み始め、秋田も同様です。大いに期待を寄せています。東京大会は今まで無かったような老若男女?の期待を一身に集めているのではないでしょうか。
さて、3月で定年退職してから、引き続き非常勤講師を務めています。秋田県は再雇用の制度はないのですが、教員不足のため、たいてい引き留められます(そのくせ教員採用数は非常に少ないのです)。週8時間3日です。昨年まで教科を担当していた2年生のクラスが、授業中うるさく勉強に意欲が少ないので、3月まで我慢をすれば、と考えていたのですが、結局週8時間そのクラスだけを担当することになりました。それじゃ卒業まで面倒見よう、と考え直し、いまさらですが、もっと興味を持てるよう授業を工夫しようとしています。担当する授業時間だけなので、非常にゆったりとした日々を送っています。学校行事なども、つい先日までは先頭になって取り仕切っていたのに、いまは離れた場所から、幽体離脱して見下ろしているような気分で見ています。不思議な気分です。
授業ですが、実習棟の教室を自分専用とし、そこへプロジェクターを常備して授業をしています。理科室や音楽室のように、各教科の教室がないのが不満でした。欧米のように、教師の教室があればと思います。また、受験は関係ないのと他のクラスと進度を合わす必要もないので、理解できるまで時間を使っています。今、中間試験中なのですが、数字は見るのもいやだ、と言っていた生徒達のほとんどが、構造計算の初歩である「反力を求める」事が出来るようになりました。授業中も静かになってきましたし、質問もするようになりました。3年生になったせいもあると思いますが、失望しかけた昨年がウソのようです。生徒に「頑張ってください」と励まされました。分掌の仕事の合間に授業をするような状況から、余裕を持って日々暮らしている気がし、授業の準備も改めて勉強している気分で、とてもおもしろいです。
組合や地域での運動は続いています。また、「にほんご教室」への比重も大きくなったので、次回は外国籍の子ども達のことを話題にします。
とらぬ狸@秋田
最後の高生研な日々
消閑亭です。
5月12日・13日に開かれた全国委員会で、ある人が「高生研の仕事がなくなったらどうやって毎日を過ごすのか」と、いらぬ質問をしてきた。心配無用である。というよりも、早く、高生研の仕事がなくならないかと願う日々である。
5月はけっこうな忙しさであった。
連休のはじめにようやく「高校生活指導」の青木書店刊行版最後の号(6月10日発行、夏号)に掲載する「論文」を脱稿した。「論文」というより「老年の主張」のような駄文であるが、興味があったらご笑覧いただいきたい。題名は「後期戦後における教師のあり方」。
この最終号では、当然今まで連載してきた「消閑亭緩々日記」も最終回である。これを書き上げ、自分で印刷所に入稿したのはまだ先週のこと。
思えば、この連載は、現役中の2003年秋号から「今季の3冊」として始まった。3年間12回続き、退職した2006年秋号から現在の「消閑亭緩々日記」となった。それが6年間24回。合計で9年間36回の連載となった。
皆さんの応援があって何とか続けることができた。
先週末には千葉高生研の「会員通信」をつくり上げた。春のゼミや全国委員会の報告など16ページである。土曜日に発送したので今日あたり着いたであろう。この「会員通信」も年間4回、休まずに発行してきた。今回の号が最後から2回目で、8月には最終号になる。私がつくるのが最終ということでなく、千葉高生研は8月で解散するので、本当の最終号である。
その最終号には、千葉高生研解散パーティを10月に千葉市内のホテルで開催することを告知した。その予約をとったりするのも結局、閑人と思われている私の仕事である。本当はそんなにヒマなわけではないが、まぁ、現役の諸君よりもヒマだろうということでこういうことになる。
さて、今週末は、「高校生活指導」最後の常任委員会校正をわが家でやることになっている。Kさんが制作し、校正済みのものを、念を入れてみんなで見る作業である。これを午前中に行い、午後からは、最後ということで、「メキシコ料理の会」を行うことになっている。TさんやFさんが腕をふるって、メキシコ料理を作ってくれるのである。
こんなふうに、毎日けっこう忙しい「高生研な日々」である。
6月に入っても、「全国通信」最終号、東京大会「研究紀要」、さらには最後の「高生研総会資料」の作成と続く日々が待っている。
もうすぐ来る解放された日々に思いを馳せながら、もう少し頑張る所存である。
ところで、皆さん、早く東京大会に申し込んでほしい。現在、申込人数は22人である(たぶん)。
もっともまだホームページにリーフレットや申込書が掲載されていないので、どうやって申し込めばいいんだ、という感じかもしれないが…。
PTA総会の一日
4月に転勤した。昨日(5月19日)は、勤務校のPTA総会だった。どこの高校でもそれほど違わないと思うが、私の一日を紹介しよう。
夜、飲み会があるので、同僚のS氏の車に乗せてもらって出勤。帰りは代行代金をS氏と割り勘して帰宅。S氏の通勤経路上に私の自宅があるので、飲み会があるとこのパターンで、昨日で3回目だ。
1時間目は 授業公開(保護者の授業参観) だ。ちょっと違うのは、近隣の中学校に公開授業の案内を出し、中学校の先生6名が授業を見に来たこと。私は2年3組の英語Ⅱの授業を公開。教室内に入って参観した保護者は3人ほどで、多くの保護者は廊下から見ている。おしゃべりをしている保護者もいる。小さい子を連れた保護者もいて、その小さい子に気をとられてしまう生徒もいて、ちょっと落ち着かない雰囲気だった。
授業公開の後は体育館で PTA総会 。参加率は40数%で、私の担任する2年4組は31人中14人が参加し、45.2%の参加率だ。
PTA総会 の後、支部ごとに別れて支部総会。支部長・副支部長の挨拶と支部担当職員の紹介と挨拶で20分ほどで終了。
その後、支部総会会場でお弁当を配り、昼食後1年生・2年生は学級懇談で、3年生は学年PTAだ。総会出席者が14名だったので、学級懇談参加者は10名くらいかと予想して、学級懇談資料を15部用意して教室に向かう。開始時間までに来た保護者は3名。開始を5分遅らせて懇談会を始めたが、参加者は5名だった。5人の保護者とこじんまりと懇談会を行ったが、予定の半分の30分で終了。終了後お二人の保護者が相談があるというので、個人的にお話をうかがった。
夕方から PTA・同窓会合同歓送迎会 ということで、退職された先生、転出された先生、転入してきた先生と、主任・部長クラスの先生と、PTA役員、同窓会役員で懇親会があった。私は転入職員を代表して挨拶を頼まれた。30年あまりの教員生活で、このような会は初めてだった。
(茨城のイソヤマ)
東京大会でお会いしたいですね
元気ですか。
先日、京都高生研の例会に出席しました。場所は、2013年に全国大会が予定されている素敵な校舎の同志社高校です。そこで、出会った先生たちの苦闘が忘れられません。生徒を管理統制することに疑問を感じて大学院で学んでいる先生、見知らぬ土地で緊張していた若い先生、梅酒が好きだと言っていた先生、高生研の集会にはあまり行ったことがないけれど『高校生活指導』は読んでいるという先生、東京大会でお会いしたいですね。高生研の全国大会は、自前で費用を負担してみんなで作る大会です。だから、誰もが対等に遠慮なく言える関係ができます。
1日目は、熟議民主主義について学びます。ちょっと難しそうですが、大丈夫です。どうしたら実りのある話し合いができるのかを理論的・実践的に学べるのです。続いて、埼玉と沖縄の教師から、生徒を市民にするための実践的な提案、これにコメントするのは、北海道、青森、東京の研究者と教師です。200名余の参加者が楽しく明日からの仕事に役立つ意義ある話し合いをします。そして、交流会は、どれに出ようか迷うほどの魅力的なものばかり、おいしいお菓子をいただきながらセクシャル・マイノリティの方と多様な性を語り合う、居酒屋で自分の夢と高校の幸せとは何かを語りあう、東京の元校長先生の教育改革のお話、「もやい」に出かけて若者の居場所論を聞く、熟議民主主義の続きを語りあう、高生研を誕生させた一人の竹内先生のお話、交流会は参加者がこの指とまれ方式で作れます。
久しぶりに会いたいですね。手作りの梅酒を持っていきます。 望月
「揉め事」
大阪のKです。私は中学生の時に吹奏楽部、大学時代は管弦楽部に入っていて運動部には縁がありませんでした。それなのに現在、女子バレーボールの顧問をしています。顧問は私を入れて4名いますが、全員がバレーボール未経験者で指導ができない状態。この状況は昨年度(2010年度)から続いています。一番かわいそうなのは選手たち…毎日の練習はキャプテン(Aさん)が指導します。毎日の練習メニューもAさんが考えて他の選手の技術指導をしてくれています。顧問の役割は、毎日の活動付き添い、体育館練習日程の調整、対外試合の申し込み、公式戦の付き添い、揉め事対応。昨年度は、この「揉め事」対応に追われていました。
Aさんがキャプテンとして部を引っ張って行くことになったのは、彼女が2年生の時の6月から。当時、彼女と同じ学年(2年)に5人、後輩にあたる1年生が7人、部に所属していました。Aさんは前任の指導者のやり方を真似ようと苦戦。「はい」もしくは「いいえ」で応答する世界、Aさんの言うことは絶対服従、Aさんの気に入らないプレーをした選手はコートに入らせてもらえない…夏休みに入った7月末、前任の指導者が、勤務先のバレーボール部員を引率して練習試合の相手になってくれるとのお話しが。私たち顧問は、この練習試合がクラブの雰囲気づくりのヒントになればいいなと考えて、この練習試合を受けました。Aさんも、久しぶりに前任者と会うことを楽しみにしている様子でした。しかし、この試合の話しを受けてからAさんの技術指導はエスカレートしていきます。「こんな型(フォーム)では先生に見せられへん」「何回も同じこと言わせんといて」「前に教えたことができてないならコートに入らんといて」「ボールに触らんといて」。1年生は7名中5名がバレーボール経験者でしたが、Aさんのこのやり方でどんどん萎縮していきました。さらに練習試合の最中には、前任者から「中学生のバレーが抜けてない」と言われてしまいます。Aさんは練習試合のあとすぐにこの先生の元へ駆け寄り、泣きながら指導を仰いでいました。そこでAさんが何を話して泣いたのか、はっきりとはわかりません。しかし、その後夏休みの練習で心を痛めていく選手が出始めました。
8月4日、2年生のBさんが朝イチから学年の先生の傍で大泣き。クラスの心配ごとかな?と思いきや、バレーボール部のことでした。事情を聴くと「Aさんのやり方にはついていけない」という訴え。この日は午前中が練習でしたが、Bさんはユニフォームを持ってきていませんでした。顧問である私と一通り話しをして、Bさんは泣きながら帰宅しました。私が職員室に戻ると、男子バレーボール部の顧問のN先生(女性)が話しかけてきてくださいました。「最近の女バレ、雰囲気が異様ですよ。コートに入れてもらえない選手が何人もいる。体育館には頻繁に行ってあげてください。」私たち顧問は、技術指導をAさんに任せきりにしてしまい、あまり体育館に足を運んでいませんでした(練習開始を練習終了後の集合で顔を合わす程度)。ここでようやく私は、Aさんがかなり追い詰められているのではないかと思い当たるようになりました。
この日、練習時間のほとんどをミーティングに充てました。私が代弁したBさんの訴えを引き取って、選手達は積極的に意見を出してくれました。「楽しくバレーをしたい」「Aさんの指導は厳しいけど、頑張ってついていく」。Aさんの気持ちもここで確認しました。彼女は、楽しいバレーではなく強いチームを作っていきたい、と言って泣き崩れました。
ミーティングの最後に私はこう言いました。「なぜバレーを始めたのか、初心はどうだったのか、皆にはよく思い出してもらいたい。根本には楽しさがあるのではないのかな。上手くいかないことがあっても、Aさんには、部員に罰を与えるようなことはしないでほしい。Aさんには技術指導を任せきりにしてしまってごめんなさい。Aさんが頑張ってくれて頼もしいけれど、一人だけでこのクラブを引っ張っているとは思わないでね。2年の仲間も頼って、強いチームを作っていこうよ。」
Bさんはその後、N先生の励ましにより女子バレーボール部に戻ってきました。しかしBさんと入れ替わるように、「Aさんのやり方についていけない」という同じ訴えで一人また一人、退部していきました。辞めていった人たちへの聴き取りは私が一手に担いましたが、皆一様に心を痛めていました。「死なない程度に大怪我しないかなと考えてしまう」ということを言う人もいました。クラブを辞めるということも許されない雰囲気になってしまっていたのです。あの8月のミーティングから、Aさんはますます固い殻を作ってしまったようで、顧問の先生に対しても、体育の先生に対しても、男バレのN先生にも、反抗的になっていきました。
なぜこんな状況になってしまったのか、してしまったのか、Aさんの引退を間近にして、いま振り返っているところです。
細腕三学年主任奮闘記④
沖縄の照屋です。先週までは梅雨時期とは思えない快晴の日が続いてましたが、今週に入って再び雨が降りしきっています。沖縄では公共交通機関がバスとモノレール(→那覇市内のみ)だけなので、雨が降るとすぐに渋滞が起きます。車で同じ距離を行くのにも、晴天時と雨天時では到着時間がかなり変わります。翌日に大切な用がある時には、前日に天気予報をチェックした方がいいですよ。
さて、「カーディガン着用許可」について前回からの続きです。昨年5月の生徒総会での職員への訴え・職員会議での話し合いを経て、その冬から「冬のお試し期間」を設けてカーディガン着用が認められました。ただ、着用が完全に許可されたわけではなく「冬のお試し期間」中(11月以降)に累計15人を越える違反者(男子:学ランを着用しないでカーディガンだけを着ていると違反/男女共通:黒・紺系統以外の色のカーディガンを着用していると違反)が出た場合、どんなに寒くても、その日を境に再びカーディガン着用を一切禁止するという条件付きでした。
11月中旬、衣替えが行われました。1週目、2週目は順調でしたが、3週目からポツポツと違反者が出てきました。会議室前の黒板に、生徒指導部の先生が「カーディガン違反者数」を書いていくのですが、12月初旬には違反者が累計5人。しかも全員が三年生(!)でした。三年担任団はもちろん、僕も三年生の授業「せっかく認めてもらったのに、ここでまた禁止になってしまったら、どうなると思う?生徒総会で生徒会のユウコ(仮名)が勇気を出して発言してくれたことが無駄になるし、先生方も「やっぱり出来ないじゃないか」って思ってしまうよ。お互いで注意し合って、何とか今後の違反者はゼロにしよう!」と呼びかけました。
しかし、違反者が一人、また一人と一週間に1~2人のペースで増えていきました。12月中旬には、9名。しかも、1人を除いて違反者は全員三年生でした。職員の中には、「三年生はどうせ3月に卒業で学校には残らないんだから、違反して取り上げられても何とも思ってないんじゃないの? 学校に残る1・2年生の気持ちは全然考えてないよね。」と言う人もいました。それを聞いて悔しかったけれど、その通りだと思いました。もし、このまま違反者が15人を越えてしまったら、下級生と三年生の間に深い溝が生まれるばかりか、今後何かを学校側に要求する時に「自分たちで要求したカーディガン着用のルールが守れなかったではないか」という事で要求がはねつけられる事になってしまいます。カーディガン着用要求時よりも、もっと厳しい状況になってしまう可能性がありました。
三年生世話係として、その事態だけは絶対に避けたいと思いました。
「何かいい手はないものか?….」 と悩んでいたある日………(次回に続く)
8月11日(土)の高生研 東京大会に参加します。
群馬高生研 稲葉 淳
高生研という組織の中に有志による新たな主体が立ち上がった
今からちょうど3年前、2009年5月の全国委員会において「2012年の大会までしか現状の常任委員会体制は維持できないことを確認する」という意味での「常任委員会の解散」が提起されました。新たな研究活動と組織活動の主体について高生研は討議すること、常任委員会は、その有志による討議に財政面を除いて介入しないこと、有志による討議の場を全国委員会や総会に保障することを提起し、全国委員会はそれを承認します。それをうけるかたちで絹村と藤本は、有志による組織検討委員会を立ち上げることを呼びかけます。
2009年8月の大阪大会総会終了後、十数名の有志による組織検討委員会が立ち上がります。
2010年8月の札幌大会総会では、組織検討委員会の「個人会員制を基本とし、有志グループの活動を中心とする」という検討結果が提起され、これが、現在の新会則案の原型となっていきます。また検討結果を受けて新高生研仮事務局が設置されることが決まります。
2010年12月の全国委員会終了後、17名の有志会員が集まり、新高生研仮事務局が発足しました。これまで10回以上の会議を重ね、新会則案、財政、新機関誌などについて討議を重ね、新体制の準備を整えてきたのです。
このようにして高生研という組織の中に有志による新たな主体が立ち上がったのです。高生研は、有志による新しい主体の出現にこだわってきました。この有志の精神は、新高生研の新しい組織原則にもなっています。
高生研は解散しないのですから従来の高生研とはまったく別の組織が生まれるのではありません。かといって、たんなる会則の変更でもないのだと思います。「新組織の発足」でもなく「組織の改変」でもないのです。あえて言うならそれは「新たな主体による再組織」ということになるのでしょう。これは、民間教育研究団体における大いなる実験的試みと言えるのかもしれません。
全国通信春号の「新高生研仮事務局からの経過報告とお願い」もあわせてお読みいただければ幸いです。
(新高生研仮事務局長 藤本幹人)
東京大会を考える(その④目撃 東洋大学 白山キャンパス)
東洋大学白山キャンパスを目撃してきました。

全国委員会のあと、第50回高生研全国大会2012東京大会会場の下見に行ってきました。
百聞は一見にしかず。話に聞いていた以上のものがありました。
ビジュアルに報告します。(写真をクリックすると大きく表示します。)
地下鉄白山駅をA3出口から出ます。向こうからリクルート姿の若者が大勢やってきます。
これは東洋大でセミナーか何かが行われてたに違いないと、その人並みが来る方向に進んでいきます。
125周年記念棟の建設工事を左手に正門にたどり着きました。
東洋大学正門。(写真①です)

奥にそびえるのがシンボル的建物2号館。この奥に分科会や全体会が行われる6号館や
大交流会が行われる食堂スエヒロが3号館地下にあります。さすがにこの日は日曜の夕方で食堂は閉まっていましたが、
6号館はしっかり見てきました。
6号館、西側からの外観。
(写真②です。こちら側からの出入りも出来ますが、やはり最寄りの地下鉄は白山駅とか千石駅になります)

分科会が行われる講義室を吹く抜け廊下2階から撮影。(写真③です)

吹き抜けの周りの廊下には、思い思いにくつろげるベンチがそこそこあって、互いの息づかいが感じられるいい空間になっています。
学食ランキング上位に位置する食堂はこの6号館地下にあります。
「なるほど、これなら人気があるのも納得。」といった建築空間なのでした。
大会中、そこが開いているかはまだ分からないそうです。
それよりもなによりも、私たちがおもいっきり学習できる環境が整っていることを確信しjました。
(アンドウ@みえ)
「佐藤レポートの司会をして」
玉名工業高校 藤川 秀一
分析会が始まるやいなや、大阪高生研代表の中村さんが班分けの妙技を見せてくれました。みなさんも活用してみて下さい。
参加者に年頭の抱負を漢字一字で書いてもらい、何人かにその意味を発表してもらいます。次に漢字の画数の順に一列に並んでもらい、5班に分けるなら「いち、に・・ご」と号令を掛け、5班に分けるというものです。「班分け」一つとっても、これまで大阪高生研は様々なやり方を教えてくれましたが、これはまたユニークな方法です。パクリたいと思います。
さて佐藤レポートは、20年間ずっと生徒会やクラス担任ばかりを担当してきた「HR派」教師が、慣れない「学年生徒指導主担」をすることになった。近隣有数の厳しい生徒指導が行われている学校で、「軟弱生徒指導主担」は、1年目の若手教師とタッグでどう取り組んだか、という内容です。
1年目の若手教師とタッグでどう取り組んだかの部分は、学代会議(各クラスの委員長、HR委員が出席)による学年自治の追求、具体的には「綱引き大会」や「球技大会」の自主運営、クラスの「席替えのルールづくり」の取り組み、さらには学年の生徒たちの要求をアンケートで募り、その中から「勉強会」を実現するなど、興味深い内容なのですが、当の若者教師のご都合が悪く、しかも時間的制約もあり、論議出来なかったのが大変残念でした。
今回の分析会の特徴は、参加者のみなさんの意欲的な質問(レポーターへの聞き込み)によって、佐藤さんの報告そのままからは見えなかった側面が明らかになったことでした。
例えば、「指導拒否は生指扱い」「頭髪違反は帰宅指導」など、いわゆる「毅然とした指導」は佐藤さんらしくない指導のやり方ではないか、という質問が明らかにした側面は、佐藤さんが生徒や親といつもじっくり話し込み、帰宅指導は極力避けることが出来るよう、事前に粘り強い語り掛けを続けていたということです。その意味で佐藤実践は排除しない実践だと言えるのではないでしょうか。さらに言えばゼロ・トレランス的な学校をまず学年から換骨奪胎していく学校づくりの実践と言えるでしょう。
また「だめなものはだめ」と厳格に生徒に迫ることの出来る同僚教師が、共に生徒指導に取り組む中で、次第に柔軟な指導もされるようになったのも、異質なものを異質なものとして終わらせない佐藤実践の懐の深さではないでしょうか。
今年の夏の東京での全国大会では、このレポートがぜひ一日通しの分科会で論議されることを期待します。 以上
TPPではなくTP参加
東京高生研 上條隆志
教師になったころと今と比べて、一番変わったと感じているのがLHRのあり方です。前はどんな学校でも、LHRは生徒自身のものであり、生徒が自主的に計画を立て実行するのが原則でした。従って連絡はすべてSHRで済ませます。それが、生徒会から降りてきた議題を討議する以外は、進路ガイダンスか教師の講話など大多数が「先生の時間」に変わってしまいました。生徒の企画は、遊びとか、散歩とか、食べ物をつくるなど多くなりますが、それも楽しい。もちろん教師からも提案して討論もしますがあくまで生徒の議決を経てです。私も脳裏に浮かぶのは高校時代の「男女手つなぎおに」のあのほのかなときめきです。
さて前回に続いて、物理の授業です。生徒からみんなで何かやりたいの声が大きくなってきました。物理のレパートリーには「電気パン」「べっこう飴」「綿あめ」がありますが(クラスで文化祭に物理縁日というのをやったことがあります。メインは黒板消しクリーナーを密かに分解してつくったホバークラフトです。)みんなの意見は、ぜひ学校でたこ焼きをやってみたい、ということでした。うーむ。さいわい物理実験室は強力な電源を備えています。いきましょうか。
誰か準備を担当してくれるかなの声に答えて、数名の実行委員会ができあがりました。ことは秘密を要します。他に口外せず知られず進めることにします。たこ焼き器数台を家から持ってくる人を決めること、材料、調理器具、石鹸などの調達があります。計画進行状況を共有しなければなりません。黒板で連絡しますが、符牒を決めましょう。タコヤキパーティーの頭文字をとって「TP」でどうか。これには爆笑。以後しばらく流行語となりました。「今日、TP参加についての話し合いがあります」。
さて当日、5時間目なので昼休みから準備開始。数名が近くのスーパーに買い出しに。教室の廊下側は締め切り、においが洩れないように工夫を凝らします。たこ焼き器を囲んで談笑しながらみんなでつくります。いい手つきです。Kさんがにこやかな笑みを浮かべながら「最初に焼いたのは先生に食べてほしいので」と持ってきます。うれしいなあと一口でほおばると、なんとわさびが充填されています。鳴り響く携帯のシャッター音。これが若者の得意ワザですね。チョコレートとかいろんなものを入れています。
ギターで歌を奏でる2人。「先生の曲を作ったので」と演奏してくれましたが、歌詞がないのでほめているのかけなしているのか分からず。
私は食中毒を起こしてはいかんと老婆心から「そこまだ早い!もっと焼いて」と注意して回ります。こういう企画の楽しみはいろいろな個性の生徒がそれぞれの良さをどのように発揮するかをみられるところですね。「やっと高校らしい思い出がひとつできました」とはある生徒の言です。