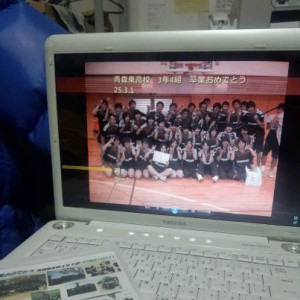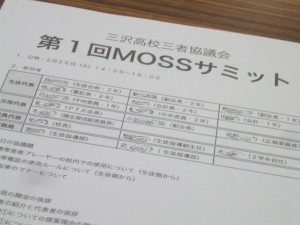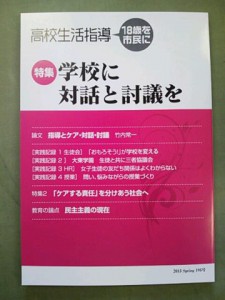部活動・スポーツの指導だけに収束させず、
学校内すべての「暴力」を鎮めるために
~「体罰」問題を考える緊急集会で明らかになった3つの論点と実践の方向性~
大阪高生研事務局
「体罰」問題を考える緊急集会「今、あらためて“指導”を考える~学校における体罰・暴力をなくすために~」(1月31日開催)は、部顧問の体罰を苦に自ら命を絶たなければならなかった若者の無念の思いに哀悼の意を表し、この問題を私たちひとりひとりの指導を検証する教育的議論に引き寄せることを目的とするものでした。
集会の冒頭、弁護士の方から、暴行・障害・傷害致死罪と最高裁判例が示され、何人も「緊急避難」と「正当防衛」以外に「人の身体に対する有形力の不法な行使」は許されないことが確認されました。
その後の集会の討論は、3つの重要な論点とすすむべき実践の方向を明確に示すものになったと言えます。
第1に、体罰という暴力が子どもにどれだけ深刻な影響を及ぼすかについての確認です。
神奈川からメールを寄せてくれたある保護者は、ご自身の子ども時代の被体罰経験から、体罰の恐怖が子どもから考えることを放棄させ、見せかけのがんばりと自己肯定できない不安のなかに生きることを強いていくと指摘されました。参加されたジャーナリストからは、取材を通して、自分がされたことではなくても体罰を見せつけられること自体の恐怖が報告されました。研究者からは、ある意味で正常な恐怖心すら「心の弱さ」のせいに追い込む自己責任論を媒介して被体罰経験者のなかに体罰肯定論が生まれてしまうことが調査結果に基づいて発言がありました。
さまざまな体罰容認論・必要論が根強い中で、まず私たちが肝に銘じなければならないことは、体罰に従順な子どもではなく、体罰を「おかしい!」と言える、そして必要なSOSを、さまざまな方法で発信できる子どもを育てようという決意です。
第2に、私たち自身があらためて指導とは何かを問うことです。
人を指導することを生業(なりわい)にしている私たちこそ、誤った指導観を克服する不断の努力を自己に課さなければなりません。今、学校現場には、マネジメントにもとづく目標‐成果主義が浸潤し、子ども・生徒を自己の思いどおりにすることが指導であり、思いどおりに動かせる教師がよい教師であるかのような眼差しが強まっています。体罰・暴力は人を支配する快感を手っとり早く与えてくれる「麻薬のようなもの(教育研究者の発言より)」です。その快感と引き換えに、尊敬と信頼に基づいた指導‐被指導関係は捨て去られてしまいます。
また、剥き出しの暴力や体罰のみがその関係を廃棄するのではないことにも注意を払う必要があります。罰則を細かく定め、違反した場合は厳格に処分を行う「ゼロトレランス」的生徒指導は、多くの場合、生徒と教師の応答を断絶し、よりシステマティックに人を傷つけ支配しようとします。私たちは制度や構造に組み込まれた無意識の暴力性もまた、言語化する努力が必要でしょう。
集会の中で元大阪市教育委員長が述べられたように、指導とは「問いかけと応答」から成り立つ本質的に相互関係行為です。指導する者は、指導される者とともに現実を読み、感じ取り、どうなりたいのか、どうすればそうなれるのか、指導者としてやれることは何なのかを、互いに問いかけ応答しながら進みます。しかし、生徒が発する問いかけや応答は、必ずしも前向きでないかもしれません。むしろ、指導に対して否定的な様相を見せることのほうが多いでしょう。
そんな時に湧き上がる怒りや暴力的な自分をどう鎮めていくのか。
私たちは、指導の「~べからず」を数えあげるのではなく、生徒との関係を忌憚なく検討し反省しあえる場と同僚性を作りだすことに力を注ぎたいと考えます。
第3に、そのような真摯で自由な議論に裏打ちされた学校をどうつくるのかが問われています。
現場では、職員会議が、議論よりも「ホウ・レン・ソウ(報告・連絡・相談)」の場に変えられ、「上から」の眼差しのなかで教師が孤立感と無力感を深めています。価値対抗的な議論と当事者の決定をともなわない民主主義では、形式的な平等が優先され、誰も本気で責任を取ろうとしません。その行き着く先は、失敗の犯人捜しと過剰な個人攻撃と首のスゲカエです。
今、学校現場に必要なことは、暴力の過ちを克服する自浄能力を具体的にどう高めるかに知恵を絞ることです。
集会では、「今年を三者協議会元年に!」という発言がありました。大阪府教育委員会が推進する学校協議会は現場教員や生徒の代表が含まれておらず、当事者の対等な参加が担保されていません。しかし、私たちは制度を待つのではなく、実践を通じて制度を作る道筋を考えたい。教師、生徒、父母、第三者が事実を共有し、知恵を集め、お互いの他者性を尊重しながら一歩ずつ相互の信頼を回復していく地道な実践を通じて、学校民主主義をリアルなものにしていきたいと考えます。
以上、学校現場から、私たちの思いを表明します。
2013年 2月