私の勤務校では「学びの共同体」による授業改革・学校改革をおこなって4年目になります。数年前、大阪の全国大会でその状況報告をしました。学びから疎外されてきた生徒たちが学ぶことへの意欲をもつようになってきた実感はあります。今日は「学びの共同体」のもうひとつの側面、教師の「同僚性の構築」に関して近況を報告します。
「学びの共同体」には「ひとり残らず教師の成長を保障する」という理念があります。その理念を実現するしくみとして本校では教員を6つのグループに分けて、どのグループも学期に1回は授業検討会を実施しています。他のグループの検討会にも出入りできるので、やる気があればたくさんの検討会に参加できます。6月はこの検討会5回と全校あげての公開授業研究会(注)があります。
授業検討会は教師の指導の巧拙を云々するのではなく、生徒の「学びの事実」に焦点を当てた対話的な場を追究して実施しています。4年目に入って教師の世界も「学びの共同体」になったと言いたいところですが、人事異動による入れ替わりや同僚への必要以上の配慮もあり、断言はできません。でも、フツーの高校にはないOJTであることには間違いありません。
そんななか6月6日(水)の午後、県立大学の学生22名が大学の教員3名といっしょに本校の授業を観察して、その後、授業検討会をおこないました。3月に福井大学教職大学院の研究会に参加して知り合った県立大学の准教授との間でトントンと進んだ企画です。
1年生の現代文の授業を観察した後に、学生たちと90分の授業検討会を実施しました。グループ討論で出された意見や疑問に授業者である本校の教員Sさんが一つひとつ丁寧に応答しました。世話役として検討会に参加していた私はやりとりを聴いてあらためて新鮮な気分で学ぶことができました。
学生の授業観察の細やかさに感心するとともに、彼らの「学ぼう」「教えてもらおう」という意欲の高さに驚きました。「グループになったときに、先生の指示と違うことをしていた子がいた」「グループ内でできた子のものを写しているだけの子がいた。プリントを提出させないのか?」「おとなしい生徒への働きかけはできていたのか?」など意見や質問がどんどん出てきました。また、「グループ学習をする前に、個人で考える時間が必要ではないか?」という核心に触れるような疑問も出されました。以下、学生の発言で私が感心させられたことを箇条書きします。
・(授業の冒頭に示された)「メニュー」(授業の流れ)は新鮮だった。
・大学での経験で6人のグループではお客さんになる人もいるが、4人のグループだと対角線で話し合うため、しっかりと話し合える。
・文法のようにあらかじめ決まった世界の内容にもグループ学習は有効か?
・グループの意見を全体で共有するときに机を「コの字型」に戻されたのはどういう意味か?
・4人グループは笑顔で話している。一斉授業は身体がこわばっている。
・先生と生徒のやりとりが和気藹々としていた。「学びの共同体」は信頼関係がないとできないと思う。
・4人グループにしたときに机がズレている生徒は「問題」を抱えている生徒のようだ。
後に学生たちが書いたレポートが送られてくるというので楽しみです。参加された教授から教職課程の授業でもぜひこの企画をやってみたいという話もありました。このような意見が飛び交う研究会が当たり前になるような開かれた学校になることを願っています。
(注)6月17日(日) 公開授業、研究授業、佐藤学さんの講演「高校における『学びの共同体』の創造」、授業検討会 詳細は本校のHP
滋賀 夏原常明
月: 2012年6月
今こそ地方が奮い立つとき!!
みなさんこんにちは。熊本からの応援ブログです。
九州からの話題を紹介することで、第50回大会東京大会応援のエールとしたいと思います。
まず、この秋(10月20日~21日の土日)は九ブロ学習会を鹿児島市内で行います。復活大会から数えて8回目、熊本からの「押しかけ学習会」としては宮崎、福岡に次いで3回目の開催となります。この「押しかけ~」とは、九州各県が輪番で担当して主催するのがベストであるけれども、各県が主催する条件が整うまでの当分の間は、今現在活動ができている熊本が毎月の例会の一つとして県外に飛び出し、学習会を行う形態です。
現地に一人でも(全国・熊本県)会員がいるというような手掛かりがあれば、そこでやる意味はあります。企画、運営、会場確保、宿泊、交通はすべて熊本でやり、現地にお願いするのは会場の紹介や参加の呼びかけ、夜の交流会の場所選定ぐらいです。そのことで、現地の方々同士が顔を合わせることができ、また九州各県からの参加者と交流ができれば良しと考えています。今ここで、「九州に血流を通しておく」ことが当面の目標です。今大会では、過去鹿児島高生研に関わってこられ、今現在は高校再編問題に取組んでおられる中島栄一さん(著作:高文研「私は学びたい。だからーいま青春」他にも数冊)の講演、熊本高生研出身で現在鹿屋工業高勤務の田邊憲史郎さんの実践報告がメインとなります。もちろん夜の天文館を中心にさつま焼酎巡行もあります。
全線開通した新幹線でスピードアップした鹿児島までの距離感を是非体感してください。
さて二つ目は、東京大会から僅か一週間後の8月の18日(土)、宮崎の「山下道也さんを訪ねる旅」を計画しています。熊本での高生研の発祥の地は矢部高校(水道橋である通潤橋で有名)であると言われていますが、そこに灯を点したのが山下さんです。彼は今、私的通信である「こんとん座」通信の発刊、「スローライフinみやざき」という地域交流会の運営、それと哲学サークル「水よう会」の主宰と84歳の御高齢でありながら、八面六臂の活躍をされている(元全国高生研常任委員で、「集団づくりのなかで1」「同じく2」(鉱脈社)の著作者)。この「こんとん座」通信第54号に、次のような記述があったのです。
「わたし的に(若者表現を真似て)言えば、40年前から高生研の中で実践し考えてきた「集団つくり」のいちばん中心にあった(そのことも当時わたしはよくわからなかった)「核づくり」の意味が、ほんと今頃になってようやく見えてきた~」
これをみて、「えっ!あの山下さんにして…」という驚きです。僕らの科白ならともかく。そして「核づくりが話題になって、水よう会は息を吹き返した」とあります。これはもう、行くきゃない。直接会って、今まで彼が捉えていた認識とどこの部分がどう違うのかを確認したい、そして水よう会のメンバーとまた会いたいという思いが同勤する藤川、正清(座席も隣)に高じ、先の「訪ねる旅」として具体化したのです。
「授業中の活動で言うとまったく活動ができない最下位の者が、じつは集団に対してもっとも大きな影響力を秘めている」「この原則からみるとどうなるか。いちばんおくれている宮崎県は、日本に対してもっとも大きな潜在的影響力をもっている、ということにならないか。」と山下さんの著作「集団づくりのなかで2」のあとがきにあります。即していうと、九州が元気になることが、全国高生研の底上げになるのだといういうことです。えっ!なぜ最下位の者が大きな影響力を秘めているかって?それを詳しく聞きたければ、一緒に宮崎に行きましょう!!
学ぶ意欲が伝わった大学生たちの授業検討会
私の勤務校では「学びの共同体」による授業改革・学校改革をおこなって4年目になります。数年前、大阪の全国大会でその状況報告をしました。学びから疎外されてきた生徒たちが学ぶことへの意欲をもつようになってきた実感はあります。今日は「学びの共同体」のもうひとつの側面、教師の「同僚性の構築」に関して近況を報告します。
「学びの共同体」には「ひとり残らず教師の成長を保障する」という理念があります。その理念を実現するしくみとして本校では教員を6つのグループに分けて、どのグループも学期に1回は授業検討会を実施しています。他のグループの検討会にも出入りできるので、やる気があればたくさんの検討会に参加できます。6月はこの検討会5回と全校あげての公開授業研究会(注)があります。
授業検討会は教師の指導の巧拙を云々するのではなく、生徒の「学びの事実」に焦点を当てた対話的な場を追究して実施しています。4年目に入って教師の世界も「学びの共同体」になったと言いたいところですが、人事異動による入れ替わりや同僚への必要以上の配慮もあり、断言はできません。でも、フツーの高校にはないOJTであることには間違いありません。
そんななか6月6日(水)の午後、県立大学の学生22名が大学の教員3名といっしょに本校の授業を観察して、その後、授業検討会をおこないました。3月に福井大学教職大学院の研究会に参加して知り合った県立大学の准教授との間でトントンと進んだ企画です。
1年生の現代文の授業を観察した後に、学生たちと90分の授業検討会を実施しました。グループ討論で出された意見や疑問に授業者である本校の教員Sさんが一つひとつ丁寧に応答しました。世話役として検討会に参加していた私はやりとりを聴いてあらためて新鮮な気分で学ぶことができました。
学生の授業観察の細やかさに感心するとともに、彼らの「学ぼう」「教えてもらおう」という意欲の高さに驚きました。「グループになったときに、先生の指示と違うことをしていた子がいた」「グループ内でできた子のものを写しているだけの子がいた。プリントを提出させないのか?」「おとなしい生徒への働きかけはできていたのか?」など意見や質問がどんどん出てきました。また、「グループ学習をする前に、個人で考える時間が必要ではないか?」という核心に触れるような疑問も出されました。以下、学生の発言で私が感心させられたことを箇条書きします。
・(授業の冒頭に示された)「メニュー」(授業の流れ)は新鮮だった。
・大学での経験で6人のグループではお客さんになる人もいるが、4人のグループだと対角線で話し合うため、しっかりと話し合える。
・文法のようにあらかじめ決まった世界の内容にもグループ学習は有効か?
・グループの意見を全体で共有するときに机を「コの字型」に戻されたのはどういう意味か?
・4人グループは笑顔で話している。一斉授業は身体がこわばっている。
・先生と生徒のやりとりが和気藹々としていた。「学びの共同体」は信頼関係がないとできないと思う。
・4人グループにしたときに机がズレている生徒は「問題」を抱えている生徒のようだ。
後に学生たちが書いたレポートが送られてくるというので楽しみです。参加された教授から教職課程の授業でもぜひこの企画をやってみたいという話もありました。このような意見が飛び交う研究会が当たり前になるような開かれた学校になることを願っています。
(注)6月17日(日) 公開授業、研究授業、佐藤学さんの講演「高校における『学びの共同体』の創造」、授業検討会 詳細は本校のHP
滋賀 夏原常明
遂に7月例会の詳細がベールをぬぐ・・・
大阪・サトウです。
大阪高生研で「S藤」と書けば、「シュトウ」さんなのか「サトウ」なのかわからないけど、もう1人、大阪には「サイトウ」さん(20代・女性)もいるんです。
大阪高生研7月例会は、その、サイトウさんが担当してます。
<以下>
きのうの6月例会(「ぴらいち例会」)に続き、7月例会は7月31日(火)に行います。
1月例会に講演をしていただいた、埼玉県立浦和商業高校の平野先生が、定時制太鼓部から派生した太鼓集団「響」と、再度大阪へ来てくださいます!
日時:7月31日(火)12:30~16:30(予定)
場所:大阪市鶴見区民センター小ホール(地下鉄鶴見緑地線 横堤駅すぐ)
内容: *「響」による太鼓教室
*「響」太鼓講演
*「響」と参加者のお話会
「生徒が主人公」の学校で行われた実践を、生徒の目線から語られる言葉でききませんか。
***
先日、「響」の代表者が大阪へいらっしゃって、ホールの下見と打ち合わせを行いました。
私自身、例会の企画は初めてなので、メールのやりとりだけでどれだけ伝わっているか不安でしたが、今回直接お会いして話ができたので、7月へ向けて大きく前進できた実感を得ました。内容は先方におまかせ、の部分も、できるだけ具体的に話をきいておきたかったし、こちらの要望で譲れない部分は何かをはっきりさせることができたので、いい機会でした。
高生研の例会として、開催のねらいと、「響」の皆さんの公演への思いを両方参加者に伝えられるよう、がんばります。7月例会、ご期待下さい!!
(斉藤)
東京大会受付・千葉高生研より
東京大会の申込者数が44人になりました。常任委員や全国委員などでまだ参加申込みをしていない人がたくさんいます。多忙なこととは思いますが、至急お申込下さい。
群馬7
千葉5
熊本4
秋田3 東京3 大阪3
北海道2 埼玉2 三重2 滋賀2 沖縄2
青森1 福島1 茨城1 山梨1 長野1 静岡1 愛知1 京都1 鳥取1
授業中に笑うと・・
学校が強権的、圧力的になっているのが顕著になっています。
先日、同僚の若い先生が生徒を授業中にダジャレを言って笑わせようとしたら、笑わないので、聞くと「授業中に笑うと、授業態度が悪いと評価されるので、笑わない」と何人かの生徒に言われたそうです。
笑えない話です(笑)。
先の組合の定期大会で、学校協議会で有名な学校から職員会議で議論がなくなり、管理職に反対の意見を言うと翌年転勤させられるという、耳を疑う発言も出ました。
埼玉東部でもそうですが、職員会議の提出議案はすべて企画委員会に事前に提出し、審査され、職員会議は採決がないどころか、実質説明と質問のみという学校も少なくないでしょう。
生徒会の文化祭の原案を審議するHR委員会(中央委員会)でも、ほおっておくと、もう決められたこととして生徒はとらえ、修正したり、反対意見を出すことはありません。
民主主義は反対意見、対立意見があるときこそ参加者するメンバーの意見が届き、活性化するものです。
東京大会の全体講演は「今、市民像・民主主義像を問い直す~多層的な熟議民主主義とシティズンシップ~」です。
「熟議民主主義」では現代を再帰的近代としてとらえます。再帰性とは価値や判断が問い直され吟味されることです。
再帰的近代では個人に判断や行動がゆだねられるため、社会は個人化し私的な意見が蔓延します。
その結果、再帰的近代にあっては「政治」が衰退するととらえます。
私たちは民主主義はともすれば、多数決や代表制のイメージが強いのではないかと思います。
熟議民主主義は個人の見解の変容を重視します。他者との対話を通して自己をとらえ直すイメージです。
そして熟議民主主義で個人は「市民」になるとい言います。
対話と「政治」をつなげたイメージが「熟議民主主義」ではないかと思います。
田村さんは新進気鋭の若手の政治学者です。
「熟議民主主義」と高生研の実践・理論をどうつなげるか、指定討論者も2名発言します。
皆さん、是非同僚・仲間を誘って、大会に参加しましょう。
埼玉 森 俊二
ヘルプ~心がつなぐストーリー~
遅ればせながら、本年度アカデミー賞作品賞ノミネート
主演&助演女優賞Wの3ノミネートの
『ヘルプ~心がつなぐストーリー~』を観てきました。
1960年代といえば、私の中ではしっかり「現代」です。
アメリカで黒人差別が残っていたという「歴史的事実」があったことは
知識としては知っていても、
どうも体感として、感じられないというのが正直なところでした。
でも、「黒人と同じトイレを使うと衛生上良くない」というような
なんの根拠もない主張が、立派なものとして認められ、
法とされるなどという不条理なことが
普通にまかり通っていたというエピソードに
なんともやりきれない胸苦しさを感じました。
しかし、大切なのは、そんな信じられない状況から
現代の(完全とはいえないまでも)状態まで改善できたのは
この映画に出てくるような、
一人ひとりの勇気ある訴えが実を結んだからでしょう。
この映画の公式ウェブサイトのプロダクションノートには
テイラー監督の感動的な言葉が綴られています。
http://disney-studio.jp/movies/help/productionnote01.jsp
小さな主張が、世界を変える力をもつようにするために必要なことが
垣間見えるような作品です。
夏の大会のシンポジウムでの私の話の中で、
この作品のエッセンスが活かせるといいなと思っています。
大会テーマに関連して、「熟議」についてちょっと考える
最近、外で飲むとき一人酒が多くなった。群れて話しながら酒を飲むことに疲れたからなのだが、一人で飲んでいると多くの人たちと触れる機会が増えて刺激的でもある。そればかりでなく、多様な価値観を浴びることによって、日常の澱のようなストレスが解消されていくのである。
先月、こんなことがあった。
文化祭2ヶ月前、各係が生徒総会を前に議案づくりをする会議があって、私は会場係を割り振られその係会に出席した。係長の原案は、「例年どおり教壇を運ぶので、重いから怪我をしないように。」といった内容が素っ気なく2行記述されているだけ。各HRから集められた係の生徒からは質問も意見も出ず、私も発言などしたくはなかったのだが、教師の役目だろうと、「ダンスコンテストの企画にもとづいてステージは設計されているのか。昨年問題になった安全性はどう検討されているのか。」と穏やかに発言した。係長はいかにも面倒くさそうに、「そんなことは実行委員会に聞いてくれ。去年のとおりにやるだけだ。」と言い放つではないか。係長の関心は、連絡のために係員のメールアドレスを集めることにあった。少々むっとした私は、「執行部が会員にお説教するような内容が総会の議案になるのか。600人の議論に耐える原案の体を成していない!」と声を荒げた。係長の近くにいた同じ3年生がウルセエナアとつぶやくのが聞こえた。
その晩よく眠れなかった私は、翌日、生徒会顧問に係長会ではどんな議論をしているのかと尋ねた。時間がないから係長会は開いていないという。議案づくりはどうしているのかときいて、前日の様子を話すと、「まだ子どもだから、そんな次元の高いことを要求するのは無理だ。」と顧問はいった。
居酒屋のカウンター越しに事の顛末を店の主人に愚痴ると、「俺なら胸ぐらつかんで殴ってるな。」と笑いながらいった。生徒もオヤジも似たようなものだと内心思いながら、このストレスは排泄された。
東京大会のテーマと講演にかかわって、名古屋大の田中哲樹氏の『熟議の理由―民主主義の政治理論』(勁草書房)を読み始めた。わからないところは読み飛ばしているが、考え方は興味深い。上條さんに紹介されて読んだ『思想としての共和国』と対比してみると、民主主義への認識が少し深まるような期待がある。
だが、我が身も含めて現代人の日常生活に熟考の場面がどれほどあるか。ICTの発達は思考の瞬発力は鍛えたが、熟考する力は衰退させたのではないか。声高に詭弁を弄する政治家に多くの若者の支持が集まる。これは決して大阪だけの現象ではない。いいのかこんなに「未熟」になって!と、先日のストレスがぶり返してきた。ここしばらくは熟議について考えることになりそうだ。
(長野・小澤)
部活教師の悩み
大会担当なのに大会以外のことを書きます。
毎年この時期は授業をカットして保護者面談を実施しています。そして、担任以外の先生は、企業や中学校への挨拶回りと、この期間を有効(?)に活用します。
しかし、部活教師の私としては大きな悩みを同時に抱えます。この時期というのは、高校総体の予選(県大会)が実施される時期でもあるからです。授業は半日なので、練習時間は確保できるのですが顧問(私)は出られません。かつては、自分のクラスだけ面談の時期をずらしていたこともあったのですが、転勤したばかりの学校ではそれもちょっと・・・。
そんな訳で、3年生最後の練習をほとんど直接見ること無しに試合に臨むことになります。まあ、見たからと言って結果が大きく変わるかというと、必ずしもそうではないのでしょうが、それでも選手(特に3年生)には気の毒な気がします。そして、彼らは「最後の練習に先生は来てくれなかった・・・」という印象を持って散って行くわけです。
もちろん、最後の印象でそれまでが全てご破算になってしまうような関わり方はしていないつもりですが、やはり最後はもうちょっと濃い感じで終わりたいですよね・・・
片桐哲郎
学校をはなれて実践交流しませんか?
本日、各所に届いているはずの「みえ高生研通信」です。
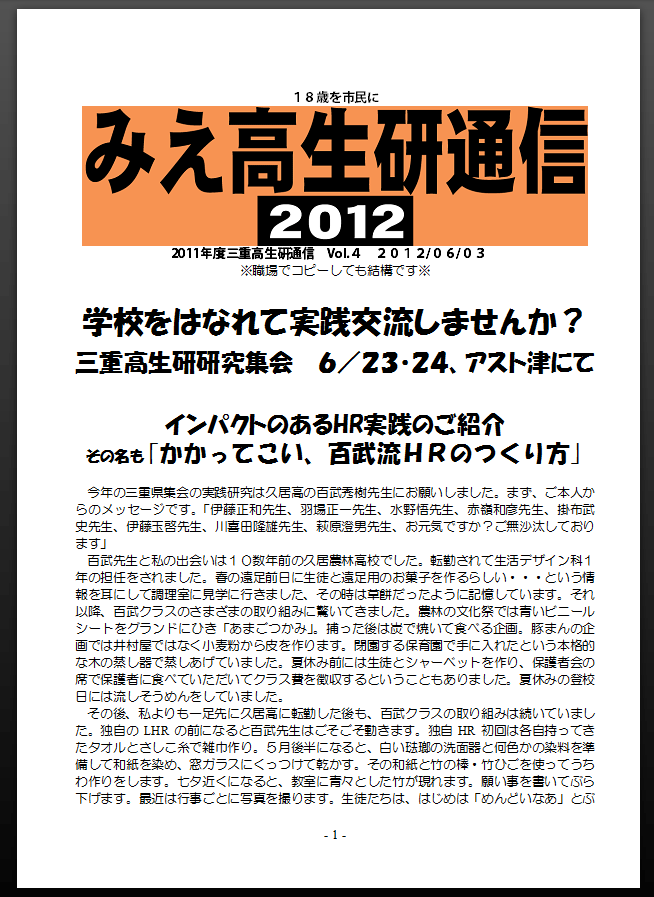
来る6月23・24日、三重高生研研究集会を行います。
今年で第32回目を数えます。
集会テーマをズバリ 「学校をはなれて実践交流」
全体会の研究協議に久田晴生さんを招いて提起してもらいます。
実践研究は百武さんというユニークなHR実践を取り上げます。
詳細は「三重高生研・討議空間ブログ」をご覧下さい。
折しも、各県の高生研が全国高生研の支部という扱いをはずされます。
三重高生研はそんな外からの動きだけでなく、内にも大きな曲がり角にさしかかっている地域高生研のひとつです。
新高生研とどこまで連動していけるか分かりませんが、この研究集会の時に行われる三重高生研総会で全国高生研との関係性も提案していくつもりです。
全国と県、持ちつ持たれつの関係で行くのが楽しいと考えるアンドウです。
地域で生きる若者、高校生(4)~「通い住民」という考え方~
そろそろ高生研らしい話題をしなくてはと考えつつ、このブログの題材を探しているのだが、ここ1週間は一つどころに落ち着くこともできず、実習巡回の保育園回りと学会の東京出張であっという間にすぎてしまった。
私の今の生活スタイルは典型的な「職住接近」である。同じ地区に私の勤める大学もある。その割には住み始めて三カ月もたつのに地域行事の一つも出てないので、そのメリットはあまり活かせてないかもしれない。と、いうのも私がいる地区が新しいまちで、回覧板など日常的なコミュニケーションツールはまだこれからという状況からである。
さて、私の所属する学科の学生は半数近くを近くの大都市出身(在住)で占められている。近隣市町を含めてこの大学を「地元」と言える学生はおそらく2割もいないであろう。また、一人暮らしの学生も2割ほどいるが、新しいまちであるが故、日常的には住民とのつながりはほとんどないようである。
しかし、まちの教育関係者からするとわが大学はある意味「顔なじみ」である。それは通学合宿や障がい児支援をはじめ、地域教育がかなり活性化されているわがまちでは、わが大学、特に教員養成を行うわが学科の学生のほぼ全員がどこかのボランティアに関わっており、サークルをしながらの複数のボランティアのかけもちもめずらしくないのである。
今日、巡回指導で訪れた保育園で、子どもへの関わり方について園長がとても感心してくださっていた。私がボランティアの話を紹介すると、「大事だよねえ。現場では勉強ばっかりで頭でっかちよりも、フットワークの軽い方が保育士としては当然、役にたつからね」と一言。また、昨日の酒席では、私の研究室の先輩であるまちの社会教育主事も「子どもに関わることで、地域も学生も、子どもと一緒に変わるんだよな」と言ってくれ、現場レベルでの大学との連携の意義を強調してくれた。
高校も大学区になって久しい。あちこちのまちから生徒が集まっては、授業終了のチャイムとともに雲の子を散らすようにいなくなる学校も珍しくない。大人のみなさん、ぜひ、通い婚ならぬ「通い住民」として、地域の学校に通う高校生や学生を社会参加させる機会を考えてみませんか?教員のみなさんは、声をかけてくれる貴重な住民の方々の受け入れ態勢を。そんなたいそうなことはいらないでしょう。基本的には「お任せ」し、生徒・学生の活躍の場となおらいの「酒席」に顔見せする。そうしているうちに、あなたも立派な「通い住民」になれますよ。
(北海道高生研 井上)
「閉じること」と「開くこと」
青森高生研 木村 一男
5月12日(土)~13日(日)、第112回全国委員会が東京大学で開催されました。主たる案件は新高生研のスタートに向けた仮事務局からの経過報告や各種提案、そしてこの夏の東京大会開催に関わるものでした。
仮事務局からは、全国通信第160号(1.29)での「新組織準備状況と移行のお願い」に続き、4月の161号では9ページに及ぶ「経過報告、お願い、暫定的会則案、会則案の説明」などが会員に向けて情報発信されていましたが、今回の全国委員会では、新高生研仮事務局長の藤本先生からその161号を資料とした実に丁寧な経過報告などが行われました。藤本先生は東京大会総会においてもこの経過報告にはあえてこだわり、時間をかけたいとのお話しがありましたが、それは2008年以来、組織検討委員会や仮事務局の皆さんが、多くの議論渦巻くなか、新しい組織のあり方や機関誌・会員通信・全国大会などについて、大変なご苦労を重ね、丁寧な議論を尽くすことを大切にしてきたその証なのだろうなと思いました。特に、「経過報告とお願い」の最後の部分(会員通信p.6)で、藤本先生は“個人的な思い”であり“具体的な答えがあるわけではないのですが”としながらも、会員相互の応答関係について「批判とケアの両輪で」と語られている部分に、私は大きな共感を覚えました。あらためて組織検討委員会や仮事務局に関わってこられた皆さんに、心から敬意を表したいと思います。
2008年、「青い森から未来を語れ」と呼びかけて取り組んだ青森大会最終日の総会において提案された「常任委員会(高生研)の2012年解散」の衝撃以来、この4年間の到達地点が今度の東京大会で示されます。「閉じること」がメビウスの帯のように「開くこと」につながっていることをこの4年間が示しているのだと思います。
閑話休題。さて、考えてみると、今回の全国委員会は新高生研に移行する前の「最後の全国委員会」となりました。1986年以来「ふたき旅館育ち」の私としては、やはりいろいろな思いがよみがえりました。また、機関誌193号が青木書店最終号として無事校了し、6月10日発行予定とのお知らせを上條先生からMLメールでいただきました。全国通信も次号が現スタッフでの最終号となります。「閉じることは開くこと」と思いながら、新高生研の一会員(シニアですが)として新たな高生研の活動に期待したいと思います。「全国フォーラム」にもたまには参加させていただきたいなと思っています。(もちろん旅費なし参加でOKです。ここがシニアの強みかと)
東京大会は、私自身にとっても大きな意味を持つ節目となる大会になりそうです。お互いに頑張って「いい大会」にしたいものです。
参加申込者37名に
東京大会の受付・千葉高生研より
6月4日現在の参加申込者が37名になりました。この1週間で13人増えました。県別の申込者数は下記の通りです。申込者が20都道府県に広がりました。
ホームページにリーフレット・申込書もアップしました。早めの申込をお願いいたします。
群馬7
大阪3 熊本3
北海道2 千葉2 埼玉2 東京2 三重2 滋賀2 沖縄2
青森1 秋田1 福島1 茨城1 山梨1 長野1 静岡1 愛知1 京都1 鳥取1
古本市
大会事務局長の船橋より
大会会場の変更があります。おっと大丈夫、東洋大学白山校舎は変更ありません。じつは
8月10日(金)から13日(月)まで、白山キャンパス6号館で、 「全国高校生ディベート甲子園」が開催されるとのこと。ずいぶん前から6号館の使用について確認してきたのですが、これは窓口となっている教学課の方のミスです。でも1号館の4Fを借用できるのでご安心ください。1号館の4Fです。この「甲子園」が開催されるので、夏季閉館と聞いていた6号館の地下食堂での昼食が可能となりそうです。この地下食堂の大学食堂人気ナンバーワンの食堂です。7月7日に1号館の4Fを視察します。
ここ数年、年に1回突然腰痛が襲うのですが、今年は5月24日の朝に襲ってきました。「うわっ来た!」。そのとき新潟県十日町市の松之山にある兎口温泉の植木屋という一軒宿にひとりで泊まっておりました。
25日に20年以上おつき合いのある「みつばち鍼灸院」へ行き、前屈み横屈みの姿勢で「助けてください。一週間後に棚田の田植えの手伝いを約束しているので、何としても行きたいんだ」というと、61才の鍼灸師は「大丈夫、たぶん大丈夫」と言いました。昔は痛い所に鍼を打ったのだけど、今は右肘の一カ所に浅い鍼を打って、「ここをいつももんでください」と言う。電動の小さなマッサージ器を当ててくれて「帰りに買って行ったら。1980円で買えるから」と言うので、ケーズ電機で1780円で買い、暇があればそこに機械を当てている。
28日も病休をとって「みつばち」に行った。同じ右肘のところに鍼を当て、それをテープで留めた。それから鍼灸師が背中に手を当ててくれる。筋肉を緩めているのだという。終わったら背筋が伸びた。不思議だ。まだ腰に違和感が残るが、6月3、4日の棚田の田植えの手伝いに行けそうな自信が湧いてきた。
いつ腰痛に襲われてもこれで大丈夫だ。安心。
大会では群馬高生研は書籍販売をやりますが、新刊書の販売だけでなく古本市をやる。
以下は私が出す予定の本だけど、1冊の価格は手数料として100円ぐらいはかかるので100円から200円の間で買っていただければ嬉しいです。これはまだ確定じゃないので変わるかもしれません。他の人が出す本もリストを作るのでお楽しみに。
1 「生活指導」復刻版 明治図書 1985年9月出版 定価138000円
1号(1959.5)~100号(1967.3)まで全20巻
2 チャータースクールの胎動 青木書店 2001年8月
3 市民社会論 青木書店 ジョン・エーレンベルク 2001年9月
4 教育改革と公共性 東京大学出版会 小玉重夫 1999年7月
5 一人で泣くのか 明治図書 服部 明 1978年
6 班のある学級 明治図書 大西忠治 1978年
7 心脳コントロール社会 ちくま新書 小森陽一 2006年
8 ワロン選集(上下) 大月書店 1983年
9 生徒が変わる時 明治図書 服部 明 1983年
10 自立への序章 明治図書 荻上憲治 1981年
11 生徒との協同をどう生み出すか 近代文芸社 服部 明編著 1994年
12 学級集団づくりのための12章 日本標準 竹内常一 1987年
13 実践的ホームルームづくり入門 明治図書 山本洋幸 1984年
14 増補 生徒会自治をかれらに 明治図書 坂本光男 1978年
15 高校HRガイドブック全5冊 明治図書 高生研編 1991年
16 教えること・育てること 明治図書 坂本光男 1978年
17 登校拒否の子どもと教師たち 明治図書 全生研編 1989年
18 対話 子どもの事実 筑摩書房 斉藤喜博 林竹二 1978年
19 日の丸・君が代処分 高文研 処分編集委員会編 2004年
20 子どもの自分くずし、その後 太郎次郎社 1989年
21 学級集団づくり入門 第二版 明治図書 全生研常任委員会 1971年
22 新版学級集団づくり入門 中学校 明治図書 全生研常任委員会1991年
23 フェミニズム教育実践の創造 青木書店 吉田和子 1997年
24 非行・問題行動をどう克服するか 明治図書 坂本光男 1981年
25 日本の学校のゆくえ 太郎次郎社 竹内常一 1993年
26 講座 高校教育改革 全5巻 労働旬報社 1995年
27 大村はま国語教室 筑摩書房 4巻と6巻 1983年
28 正常のなかの異常 三省堂 鞠川了諦 1968年
30 逆転~教室のドラマ~ 高文研 久保田武嗣 1985年
31 のびのび生活指導 高文研 神保 映 1984年
32 若い教師への手紙 高文研 竹内常一 1983年
33 学校はだれのもの? 高文研 1999年
34 高校・四季の祭典 高文研 1979年
35 授業がなりたたないと嘆く人へ 高文研 1993年
36 ある証言・高校中退 高文研 西里 治 高文研 1989年
37 教師にいま何が問われているか 高文研 家本芳郎 1982年
38 やがて・・・春~いじめと友情の物語~ 高文研 1986年
39 事件を恐れない生活指導 高文研 高橋俊之 1991年
40 この道を君は行くか 高文研 対馬文夫 1986年
41 私のなかの囚人 高文研 川口幸宏 1982年
42 私立高校~屈辱と誇り~ 高文研 豊川高校教師集団 1977年
43 流れよ、教育の大河 高文研 愛知私教連 1990年
44 海に鳴る序曲 高文研 田村宜征 1974年
45 保健室からSOS 高文研 1984年
46 教師の一日 高文研 家本芳郎 1984年
47 学園にバラを咲かせよ~東京・農産高校の学校づくり~高文研 1980年
48 特別指導 学事出版 1992年
49 入門・科学的「読み」の指導 明治図書 大西忠治 1990年
50 人間的自立と教育 青木書店 折出健二 1984年
51 高校入試制度の改革 労働旬報社 国民教育研究所 1988年
52 バラサン岬に吼えろ 民衆社 両角憲二 1982年
53 私の受けた教科書検定 東研出版 岸本重陳 1981年
新編集長よもやまばなし②―新機関誌名をめぐって―
こんにちは。新高校生活指導「18歳を市民に」編集長 井沼です。早いもので前回のブログからもう1ヶ月経ってしまいました。前回は新機関誌のデザインの話でしたが、実は出版社とのやり取りでもう少し手直しすることになっています。市販を継続するとなった以上、市場の原理に晒されます。運動団体の論理だけなら「いかに納得できるものを作るか」だけで済みますが、市場の原理に晒されるとなると「いかに売れるか」(ある意味、「見せ方」の勝負)も重要です。青木書店からの発行が193号までとなった時から、市販継続か、部内誌かの議論を何度も行い、大阪のSさんの尽力もあって教育実務センターからの発行継続が決まったわけですが、決まった以上、納得がいくことと売れることの両方追求が至上命題になるわけです。これはなかなか緊張感があります。
さて。今日は、新機関誌名が決まるまでのお話。表紙デザインの一新と併せて、新機関誌名も洒落た横文字含めて、たくさん案がありました。たとえば…
pratique(プラティーク) *「実践」を意味するフランス語
vivo(ビーボ) *「生活」を意味するラテン語
citizenship(シティズンシップ)など。
僕個人としては、横文字なら明るいイメージの「vivo!!(ビーボ)」でしょう、と密かに思っていたのですが、「何の雑誌かわからない!」という意見が相次ぎ、あえなく却下(笑)。
やっぱり、そもそも新機関誌のコンセプトは何なのか?という議論の積み上げが大事ですよね。編集委員会は何度となく、機関誌のコンセプトについて話し合ってきました。
「子ども・青年と生活をともにするという視点をたいせつに」
「生活指導実践研究誌としての性格をしっかりとおさえよう」
「すごい実践からちょっとした実践まで、複数の声を響かせながら魅力ある分析を」
「若手のかかわりを考えて、意識して」
「教師と市民がつながる機関誌を」などなど。
議論の中からいくつかのキーワードが生まれてきました。
「改正」教育基本法は、生活が文化を創り文化が社会を作りかえていく生活指導実践の法的表現ともいえる旧教育基本法第2条を削除し、統治としての教育を押しつけようとしています。このような時代に、私たちは、生活指導実践を地道に掘り起こし、記録し、多様な声によって読みひらいていくような機関誌がほしい。そして機関誌を通じて、高校生・若者の側から生活づくりを模索している先生や市民が出会い、オルタナティブな教育実践の物語に学びながら、エンパワーしていきたい。新機関誌のコンセプトはそんなところに集約されていったのでした。(つづく)
会員拡大作戦
岸田です。
会員拡大作戦の一つとして、
写真のようなものを210つくりました。
リーフ印刷は田中さん、封入は西村さん、実務は瀧内です。
大会要項もいれました。、申し込み書も。
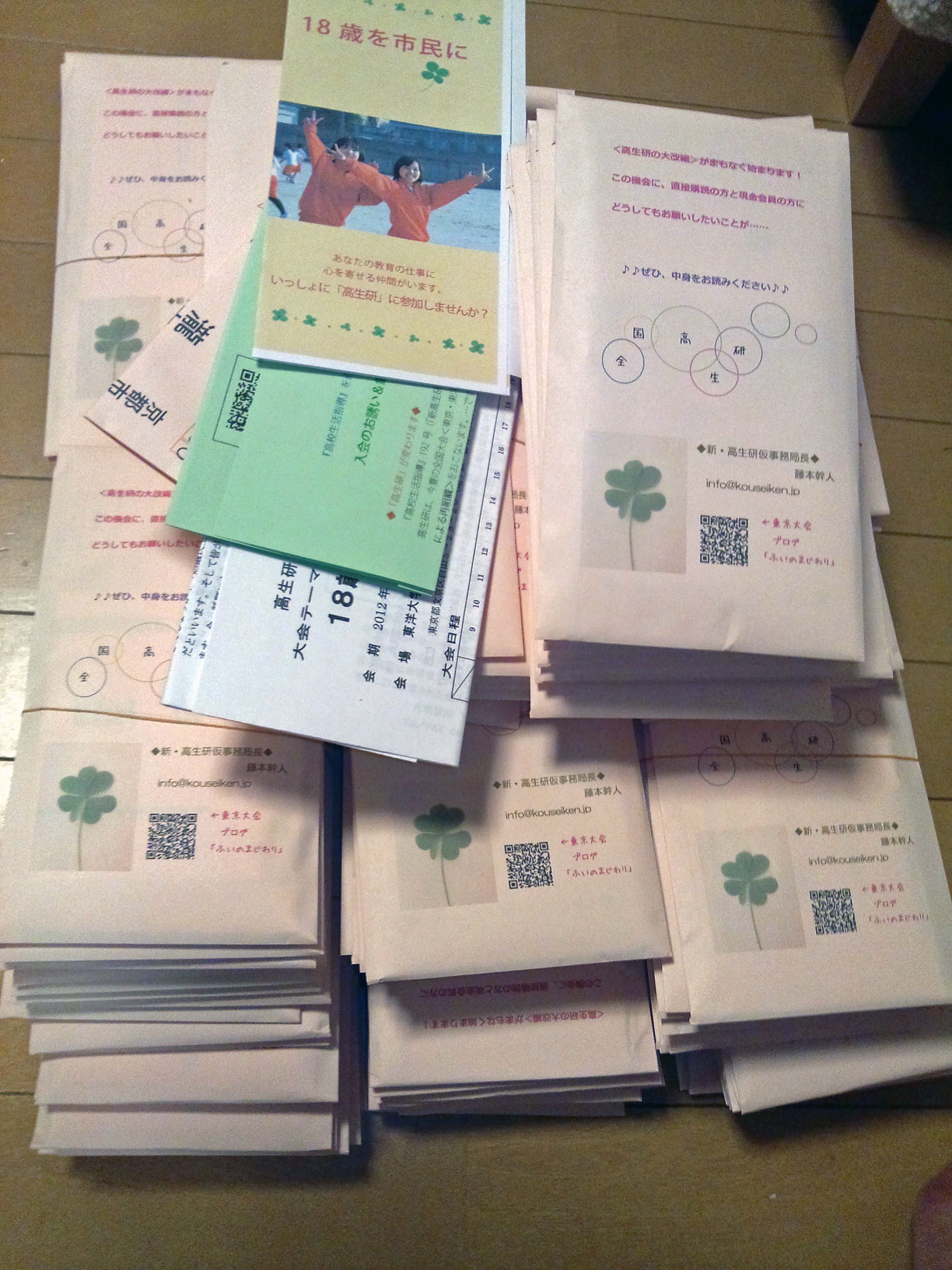
次号の機関誌発送に、
直接購読の方と、
現金会員の方に、
同封していていただくよう
内田さんに
お願いしました。
増えるといいなあ!!
『オウム真理教の真実』より
5月26日(第1,2回)、27日(第3回)に放映された『NHKスペシャル・未解決事件02
オウム真理教17年目の真実』を見た。死刑が確定した教団幹部の手紙、麻原演説を記
録した膨大な量のテープ、NHK独自の取材、こういったものをもとに、ドラマ仕立て
でオウム真理教とは何だったのかを追求するドキュメンタリーである。
ドラマ(第1,2回)は、一人のNHK記者が今は夫婦になっている二人の元信者から当
時の状況を聞くという展開になっていて、信者が信じるところの「救済」が、いつから
「武装化」に転じたのかを問うことがポイントである。ドラマでは、一人の信者が修行
中偶発的に事故死したことを麻原の指示で隠蔽したこと、及びその翌年、脱会を図る信
者をやはり麻原の指示で殺したこと、この2つをきっかけに、「救済」の名のもとで人
殺し(ポア)を容認するという方向へ舵を切ったのではないかと推理している。一方、
第3回では、元幹部の上祐の証言、教団の出版物、前述のテープなどを通して、教団設
立当初から、麻原は武装化を企図していたと分析する。私が注目したのは実は、この武
装化の時期の問題ではなく、「救済」そのものに潜む落とし穴についてである。
世の中には、困っている人、悩んでいる人を「救済」する様々な「宗教」や「ビジネ
ス」がある。「ビジネス」はともかくとして、宗教はそもそも救済することを目的とす
るものだと思うのだが、そこはくわしい人に譲るとして、私が問題にしたいのは、「救
済」の名の下、人の弱さにつけ込むことの危うさである。同番組のドラマ部分でも、一
人の若い女性が、仕事上の悩みがきっかけとなってオウムに入り、修業によって達成感
を得て、オウムに「救済」された、と感じる。
翻って、高生研でも、2009年の基調で礒山さんが「〈弱さ〉で支え合う関係を学校に
」と題して、「弱さを自覚した子どもたちと自分の無力さを自覚した教師がケアと癒し
を含み込んだ応答的な場」として学校を再構築する必要性を説いた。聞く人によっては
、これは、人の弱さにつけ込んだ「ビジネス」「宗教」とも受け取られかねない。例え
ば、悩みを抱えた生徒や教師がいて、その場に居合わせた善良な教師がその悩みを解決
してあげたいと考えたとしよう。その瞬間、その教師は「麻原」ではなかろうか。悩む
者とそれを解決してあげる者という一方向的な関係しか、そこにはないからである。こ
こに「救済」の落とし穴があると、私は考える。
では、どこに着目し、どう実践することで「救済」の落とし穴にはまらないですむの
か。
前述の元信者は、オウムが武装化していることを知り、オウムに疑問を呈するように
なる。その都度マインドコントロールされ、抜け出せずにいたのだが、地下鉄サリン事
件がおき、その直後、ついに脱出する。つまり、疑問を呈するという主体性を残してい
たことが、皮肉なことに、彼女自身を救うことになったのである。
これまで高生研は、予定調和的な「団結」に懐疑の目を向けてきた。「子どもは無垢
で善良」という楽観主義的な子ども観を排してきた。「文化祭で優勝しよう!」という
ような物取り実践を否定してきた。また、班とは「矛盾を顕在化させる装置」と定義し
たこともあった。つまり、集団の中で個々の主体性が保障されていることが必要で、そ
こで生じる矛盾・対立を敢えて引き受けることで、集団の発展があると考えてきたので
ある。平たく言えば「文句が言える」場の保障である。つまり、「救済」に関して言え
ば、「あなたの悩みを私が解決してあげる」という関係を作るのではなく、悩みを悩み
として、疑問を疑問として出せる場を保障し、その解決に向けてともに考え、実践して
いく。その際、矛盾対立が起きることも、悩む者・聴く者双方が自己変革を迫られるこ
とも辞さない、ということである。礒山さんがいう「応答的な場」には、そんな意味が
含まれているように思う。
オウムの問題は、ただの狂信的な集団の犯罪としてみるのではなく、集団というもの
が潜在的に持っている陥穽に対する警鐘としてみる、この番組を見て、私はそう受け取
った。
追伸。番組の中でもう一つ面白い指摘があった。それは、麻原が信者を洗脳する手口
が、学校で教師が生徒に発問し正解にたどり着かせる指導法と酷似しているというもの
である。「学ぶ」とはどういうことか。改めて考え直す必要があると思った。
久田晴生