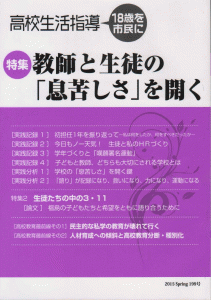こんにちは。沖縄高生研の照屋です。新年度が始まり、発足職員会議・入学式・授業開き・土曜講座と最初の一週間がやっと終わりました。僕ら教員はパタパタしてましたが、それ以上に生徒たちもしんどかったと思います。特に1年生は情報過多でオーバーフロー気味に見えました。そして僕はこの学校で初めてその1年生を担当する事になりました。かなり久しぶりの40人一斉授業で、2クラス教えます。これまで勤務してきた学校では、ほとんどの英語の授業(僕は英語の教員です)では習熟度で生徒が分かれていて、1クラスで20~30人程度でした。英語科の先生方から色々なアドバイスをもらいながら、目をキラキラさせながら説明を熱心に聞いてくれる彼らに試行錯誤で授業を行っている最中です。
さて、前回の続き。ロンドンのヒースロー空港から生徒たちと僕ら引率教員2人(合計20名)、そして現地のガイドさん(日本人女性)はバスに乗り、アシュフォード州へ。最初こそ、生徒たちは見慣れぬ車外の風景を見ながらワイワイしてましたが、一時間も経つと殆どの生徒は眠ってしまいました。長いフライトの後だったので、僕もウトウト。ガイドの方の「みなさ〜ん、起きて下さい。そろそろ着きますよ。」の声で目が覚めましたが、それが夜の7時頃だったと思います。事前に送られてきたプロフィールによると、僕がお世話になるホストマザーは仕事を退職されて一人暮らし、ノンスモーカーでペットは飼っていないとの事でした。二週間もの間、外国で、しかも他人の家で生活するのは初めてだったので、生徒たちもそうですが、僕もかなりドキドキしてきました。そうこうしているうちに、バスはホストファミリーが待つ大型スーパー施設内の駐車場へ停車(ファミリーたちはみんな車で迎えに来ていたので)!バスの窓から眺めると、一家総出で迎えに来たらしいファミリーもいました。みんな僕らに手を降ってました。生徒たちは「うわーっ!すご〜い!たくさんいる!誰が(私の)ファミリーかな(もちろん、生徒たちはファミリーの顔をまだ知りません)? 」と興奮気味。僕らがバスの中で待機してる間に、ガイドの方が先に降りて現地のコーディネーターの方と打ち合わせをしていました。間違ったファミリーに引き渡すと大変なので、かなり念入りに名簿をチェックしてました。
チェック終了後、いよいよ生徒たちがファミリーと対面します。一人一人名前が読み上げられ、バスの外での出迎えです。ファミリーに紹介されると、恥ずかしそうにモジモジしている生徒たちをファミリーたちが次々とハグし、彼女たちの荷物を運びながら車まで連れていってくれます。生徒たちがファミリーに出迎えられる度に、バスの中では歓声があがってました。生徒たちが全員ファミリーに出迎えられた後、いよいよ僕ら教員がファミリーと会います。
にこやかに僕を出迎えてくれたのは、愛嬌のある笑顔としっかりとした眼差しを持つ素敵なladyでした。挨拶をして(緊張していたので、僕の挨拶はぎこちなかったと思います)荷物を車に運び、お世話になる家へ向かって出発しました。車内での最初の会話は、多分ロンドン近郊の大雨と洪水のことだったと思います(僕らが到着する前、記録的な大雨が降り、洪水が起こった地域もあったので)。
10分ほどして彼女の家に着きました。 
さて、彼女に案内されて家の中に入ろうとすると、僕が持っていた「アメリカやヨーロッパでの常識」について予想とは違っていた事が一つありました。
それは………..(その「違い」については次回)